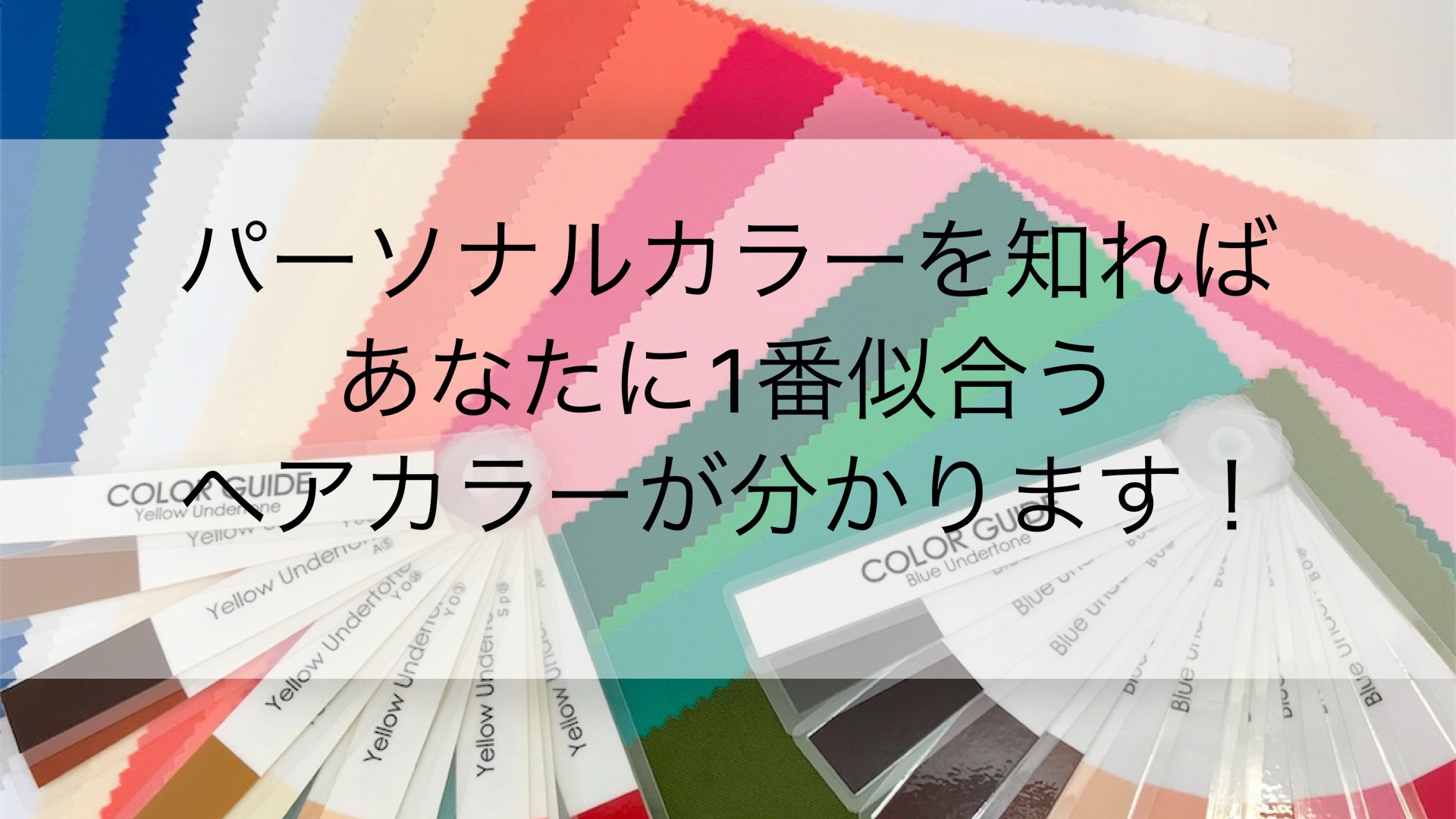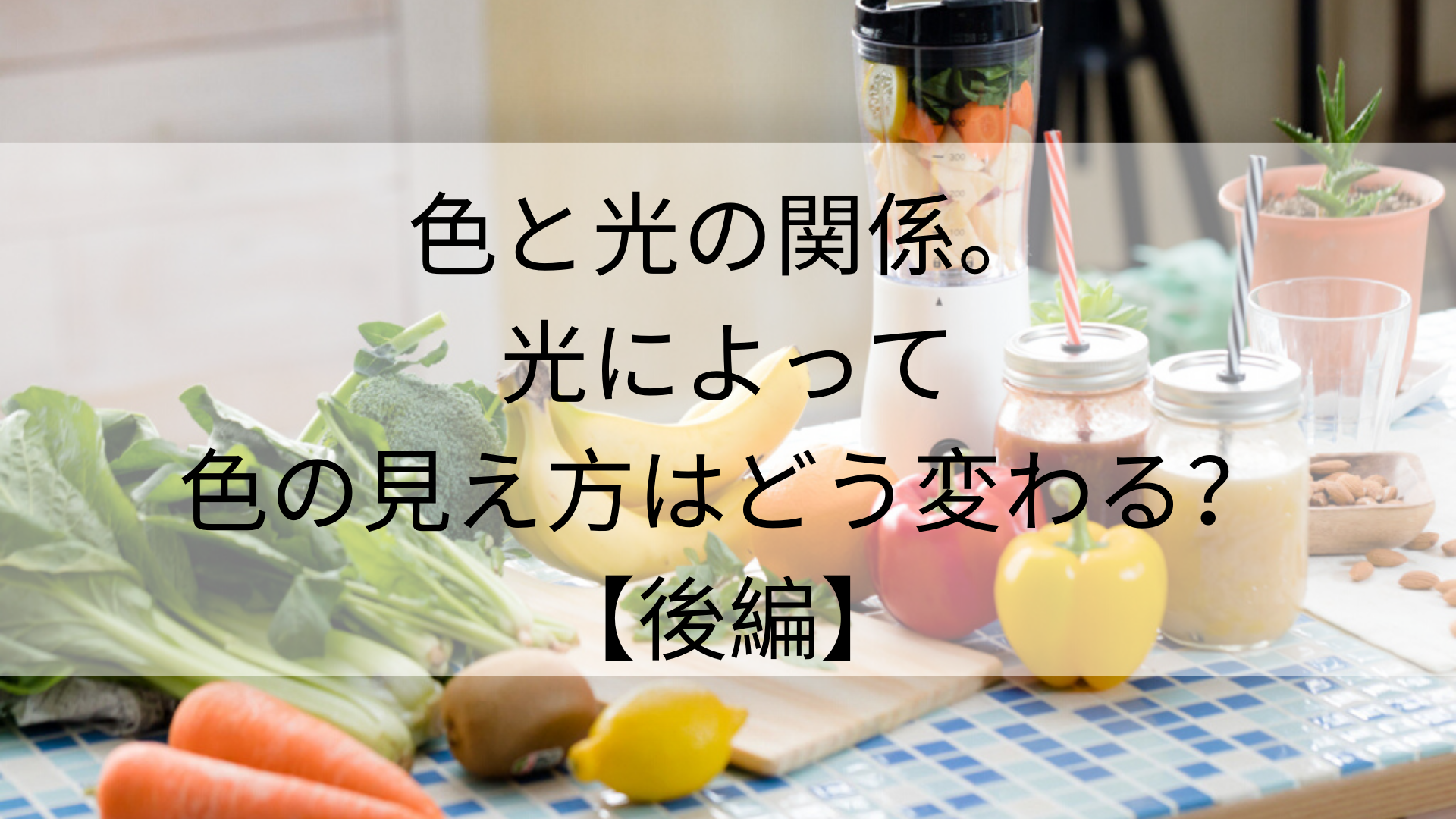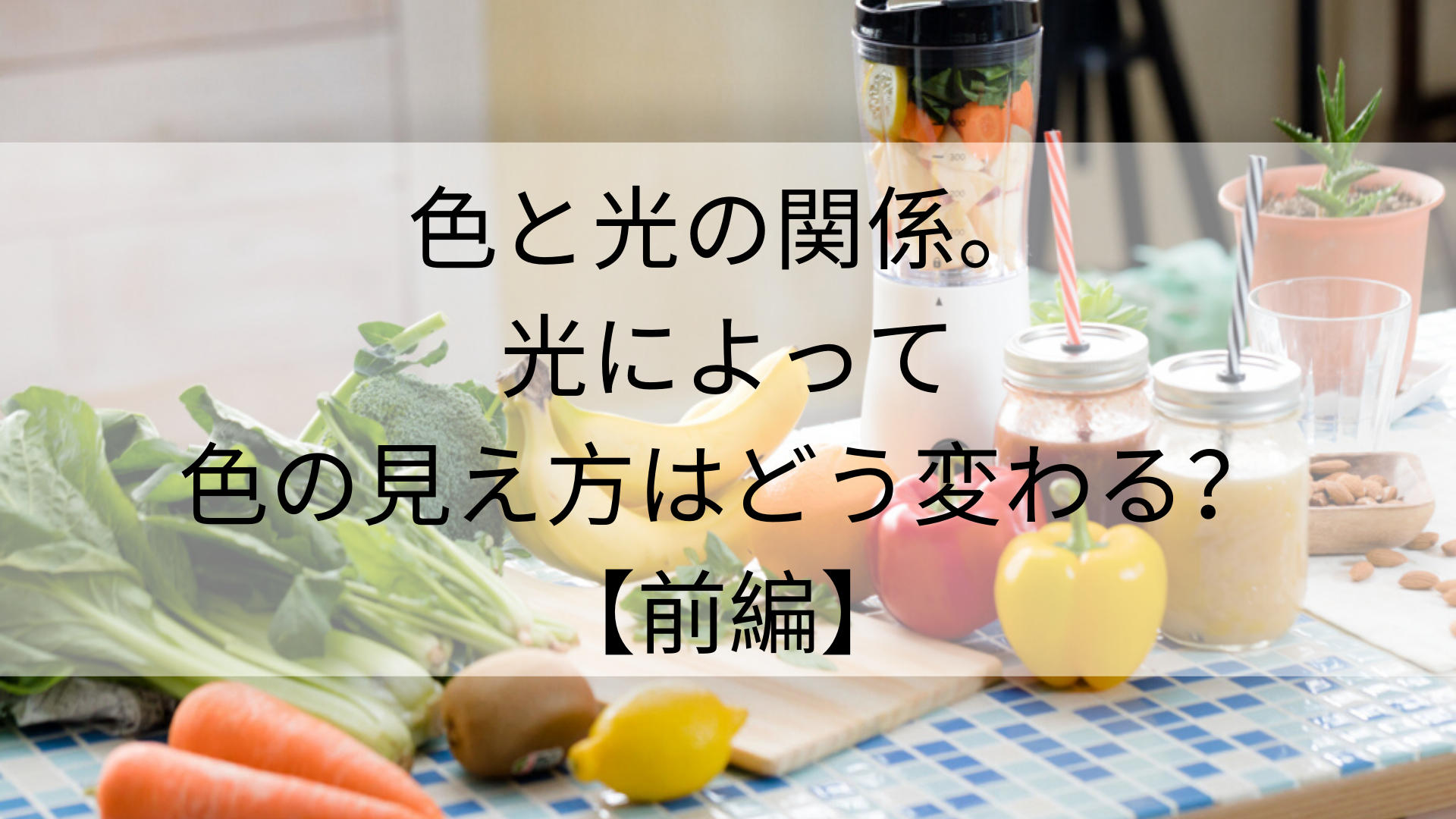前回の同じタイトルの記事では、色と光の関係性について基礎的な部分をお伝えしました。
まだお読みになられていない方は、ぜひ先に目を通して頂ければと思います。
色と光の基礎的な知識を知って頂いた上で、今回は応用編として色同士を混ぜる・色の錯覚という2点についてお伝えしていきます。
色を混ぜる?光を混ぜる?

以前の記事で、色=光とお伝えしてきました。
では、色を混ぜるとはどういうことか?
ということを、まずはお伝えしていきます。
色=光ならば、色を混ぜる=光を混ぜると言えるのか?
もちろん不正解とは言えないのですが、色彩学の考え方としては分けて考えられます。
色を混ぜるということは
皆さんも、絵の具を使って色を混ぜた経験があると思います。
色を混ぜる方法は大きく分けて2種類あります。
絵の具などのような物体を混ぜる方法と、自然光や懐中電灯などの光を混ぜる方法です。
つまり、光を反射する物を混ぜる(色を混ぜる)、光を直接混ぜる(光を混ぜる)と言えます。
そして、それぞれ3つずつ基本となる色と光があります。
理論上は基本の色を混ぜれば、どんな色も光も作れるというものです。
これを色の三原色・光の三原色と呼びます。
色の三原色

色の三原色とはシアン・マゼンタ・イエローです。
この3色を2色ずつ混ぜるとレッド・グリーン・ブルーとなり、3色全てを混ぜると(理論上は)黒となります。
例えば、プリンターは主にこの原理で着色しています。
光の三原色

次に、光の三原色とはレッド・グリーン・ブルーです。
同様に、3色中2色を混ぜるとシアン・マゼンタ・イエローとなり、3色全てを混ぜると(理論上は)白となります。
例えば、テレビはこの原理で色が見えます。
お気付きのように、色の三原色と光の三原色は正反対の性質なのです。
色と光の関係・色の錯覚
色と光では、混ぜ方・見え方が違うということが分かっていただけたと思います。
次に、色と光の錯覚についてです。
膨張色と収縮色

人間の目には、色によって大きく見える色と小さく見える色という目の錯覚があります。
大きく見える色を膨張色、小さく見える色を収縮色と言います。
簡単に言えば、明るい色ほど膨張して見え、暗い色ほど収縮して見えるということです。
なぜそう見えるのか?というと、これは明るい色が光、暗い色が影として認識する為です。
光は広がって見え、影は締まって見える(無意識に見ようとしてしまう)ためにおこる錯覚です。
例えば、白は全ての光を反射するのでボヤっと膨らんで見えます。
逆に黒は全ての光を吸収するので引き締まって見えます。
これを応用することで、例えばメイクで顔に立体感を出すなどができます。
まとめ
色と光シリーズ第2回目の今回は、色と光の三原色・膨張色と収縮色についてお伝えしました。
僕たちヘアカラーリスト含め、色を形として表現する為には必要不可欠な知識です。
しかし、メイクや服のコーディネート、インテリアなど色と光は生活の一部として身近にあるもの。
仕事上あまり必要としていないという方でも、いつもよりちょっと視点を変えて色と光を見てみると、いつもと違う発見があるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
色と光シリーズは次回で完結予定です。
次回は色同士の相性についてです。
お楽しみに ^_^